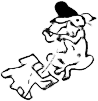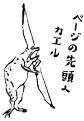『循環型社会元年生まれ、大学院生の視点』 山田 大智 京都大学大学院 修士二年 平成12年は循環型社会形成推進基本法が制定されたことから、「循環型社会元年」と呼ばれるそうだ。この言葉がどこまで一般的に浸透しているものなのかはわからないが、同年に生まれた身としては、ちょっとした縁を感じている。本トップメッセージの寄稿者としては、比較的若い人間であるから、表題のようなテーマが読者の皆様にとっても興味深いことだろうと考えた。 我々の世代は、「地球温暖化」や「リサイクル」といったキーワードを、当たり前に耳にしながら育ってきた。廃棄物・資源循環分野に進んだ自分は、相当に影響を受けている側といえるだろう。こういったキーワードに対する受け取り方は三者三様であるが、不信感に近い感覚を抱く者(自分もある意味ではその一人)も少なくないと感じている。実際、「プラスチックごみのリサイクルに関する研究をしている」と友人に話せば、時には渋い顔をされることもある。 こうした反応の裏には、国民一人一人に求められている行動や、各主体が発信する取り組みの中にあるはずの「社会全体としての合理性」が、見えにくかったり、時に曖昧で感情的な表現でマスクされていたりするケースに対して、特に若い人間は敏感になりやすいということがあるのではないかと考えている。 多くの主体(あるいは、全人類)が関わる当分野は、その分考えるべきことも多いから、社会的な合理性の担保が簡単でないことも事実である。自身の専門であるプラスチックごみに話を絞れば、分別や素材代替をどこまで進めるのが合理的なのか、完璧な一つの答えを出すのはほとんど不可能であると言えるだろう。ただし、言い切れないのでやりません、とは決してなってはいけないのが環境問題の難しさ(予防原則)である。 入り組んだ課題を多面的に考え抜き、システムや制度、技術の力で解決に導いていくことこそが、私の考える廃棄物・資源循環分野の面白さであり、こういった側面が広く知られることで、自分のように納得感をもって主体的に関わりたいと思う、次世代の人間も増えていくのではないかと思う。 まだまだ課題はあれど、付加価値を生み出していくための議論に移ることができているのは、廃棄物処理の最優先事項である衛生環境の確保や、直接埋め立ての回避(焼却による減容の徹底)といったところを、先人たちがクリアしてきたからこそだと、常々感じている。自分はまだ学生の立場ではあるが、廃棄物・資源循環分野がより良くなるよう、日々考え、行動していきたい。 |
山田 大智 |
【プロフィール】
山田 大智(やまだ だいち)
本ニュースレター編集メンバーの一人
京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻 平井研究室所属
2000年神奈川県川崎市生まれ
地元川崎における公害の歴史や、書籍の『里山資本主義』、ユニセフのリサイクル事業等をきっかけに資源循環、環境保全に関心を持つ。
2019年に京都大学工学部地球工学科に入学。
研究テーマは、
「生分解性プラスチックを導入した家庭系廃棄物処理システムのライフサイクル分析」、
「リサイクルパラメータに着目した家庭系廃プラスチックの排出実態調査」、
「バイオプラスチックの代替原則に基づいた代替ポテンシャル解析」など、
家庭系廃プラスチックを軸に手広く取り組む。
来年度からプラントメーカーに入社予定。