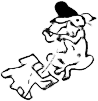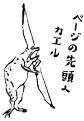~21世紀の水先案内~ 秦 めぐみ ◎6月、夏の室礼に住まいの衣替えをすませたある日、中年男性グループの来訪をお受けし接待していると、ひとりの方に「これ、虫は飛んできませんか。」と尋ねられた。「はい、入ってきます。そんなときは蚊取り線香をつけてます。」とお応えした。「この電灯、暗いことないですか。」「はい、ちょっと暗めですが、座敷は客間なのでこのくらいの明るさにしてます。」それからもいくつか質問を受けていたら、もうひとりの方が「明治時代の暮らしですな。」とひと言。うーん、なるほど、そうきましたか。 ◎私の住まいは明治2年上棟。表屋造りと呼ばれる京町家で、代々薬屋を商ってきた。平成7年阪神大震災の年、隣家はマンション立替計画が進み、その一方でわが家は住まいを公開するという重い決断をした。何度拭いてもツヤの出ない縁側の床板を恨めしく眺めながら・・。依頼を受けた原稿に泣き言を書いた日のことは、今も記憶の片隅に残っている。けれど考えてみれば、この決断が未来へ向けてのこの家の可能性を予感させてくれるきっかけを与えてくれた。建物が、よい形で生かされることを模索してきた結果、私自身、心豊かに生きることの意味を見つめなおす機会を得た。  ◎住まいの様式は、人間の生き方とも深く結びついているものだ。京都の町並みが、商人としての勘定高さを持ち合わせながらも周りへの配慮を怠らずに創られたことは一軒の京町家の造りからも見てとれる。公私の使い分けは明確。そこからは、都市住民としての気概を持ってこの地で営み続けた先人の背中が窺える。通りに面して商いの場を構えたその奥に、家人の和みの空間は広がる。表の喧騒から解き放たれた奥庭に立って天を見上げると、まるで壷中から宇宙を覗き見るかのよう。夜ともなれば漆黒に沈んだ暗闇が奥座敷までも包み込んで、天から届いた月の光が壷中にある縁先にさしかかる。そんな家が子どものころはちょっと怖かった。 メリハリの利きようは、住まいの形にとどまらず暮らし方も然り。正月、節句、祭と年中の歳時ごとに迎えるハレの日の室礼に家の中を調えると背筋はピンと伸びてあらたまった気持ちになる。また、木と土と紙に囲まれた住まいには季節の変化を感じずには過ごせない日常がある。心地よい時候は無論のこと、北風の冷たい日、むせ返るような暑い日、できるだけ機械物には頼らずにあの手この手を駆使して快適に過ごすための知恵をしぼる。殊に台所仕事はそうした日々の中枢にあって、暮らしの彩りというのはなんと豊かで忙しいものと関わるほどにつくづく思う。 手のかかることを悩ましく感じることはあるけれど、そんなときはちょっと考えをあらためる機会だと思うことにしている。祭が終わって数日後、決まって奥庭で鳴きはじめるクマゼミの声を聞けば、そう、人間も同じようなもの。大きな自然のサイクルのなかで生きている・・と。 ◎この16年のあいだに、さまざまな人々が来訪されるわが家になった。幼児から小、中、高、そして大学生。建築家、大工さん、庭師さん、主婦、独身女性。築140年を過ぎた住まいを訪れた人たちから聞く言葉は、「こんなおうち、なんかいいな!」「落ち着きますね。」「風が気持ちいいですね。」「丁寧な暮らしに憧れます。」などなど。なかでも若い人からこの家の座敷の少し暗めの照明を賞賛されると日本的感性の回帰を予感。この家での暮らし方をとても新鮮にとらえてもらっていることに、こちらのほうが驚かされる場面に出くわすことも最近よくある。自然と同化する感覚は日本の家屋の持つ特質で、新感覚としてその装置に惹かれる若者が増えつつあることはたいへん興味深い現象だ。 春に東北を襲った災いから私たちは何を学ぶのだろう。これまでの価値観を見直し、ゆるやかに軌道を修正し、足元を固めなおしていかなければいけない。そんな21世紀を生きる私たちの水先案内役の一員として、全国の郷土に息づいて建つ日本家屋は、その力を発揮してくれる存在になるのではないかと思うこのごろである。 |  |
| 【プロフィール】 秦めぐみ (はた めぐみ) ◎生家秦家住宅は18世紀半ばから近年まで薬種業を営んでいた商家で明治2年上棟「表屋造り」の京町家。京都市登録有形文化財指定。住宅を暮らしの息遣いを大切にしながら一般に公開。見学者を受け入れ、その維持・保存に努めている。生活習慣や年中歳時を伝える「くらし体験会」「料理の会」「親子会」を催すほか、一日一組限定の料理「秦家」では季節の味のおもてなしを行なう。 |